まるで日本語から直訳したような英語のイディオムに出会うたび、まったく別の成り立ちをした言語なのに同じような表現があるのっておもしろいなぁといつも思います。
“which is which?” どっちがどっち?
“scratch that” 今の取り消し!
“book worm” 本の虫
“money talks” 金がものをいう
“so” そう、なんて発音すら同じ!
“fall in love” 恋におちる、はきっと英語の和訳だと思いますが、それでもこの表現はしっくり来ると思いませんか?
夏目漱石が英語教師をしていた頃、”I love you”を「私はあなたを愛しています」と訳した学生に、「日本人はそんなことは言わない。「月が綺麗ですね」とでも訳しておけば足りるのだ」と言った話は有名ですね。
直訳では全く違うのに、同じ気持ちを表す“I love you”と「月が綺麗ですね」に英語話者と日本人のメンタリティの差が見えます。
その頃の日本にはそもそも「愛する」という概念自体、あまり親しみのないものだったんです。愛とは誰かを思って「焦がれる」ものでした。
どちらかというと“long for” 想い焦がれる、恋い慕う、という自動詞のほうがしっくり来るんですね。でもこれも、秘めておくもの。女性は特に、そんな気持ちを口にするのははしたないと思われていました。
漱石と同じ時代の翻訳家で小説家でもある二葉亭四迷はこんな背景から、男性の”I love you.”に対しての女性のこたえ、”I love you too.”を和訳するのに大変困り果て、遂には「わたし、死んでもいいわ」と訳したとか。
日本男児たるもの愛なぞ軽く口にするものではなく、月が綺麗ですねの一言で女は全てを察してやらなきゃいけないし、わたし死んでもいいわと返して両想いであることを間接的に伝えなきゃいけない。
現代の日本ではそこまで極端な察しスキルはさすがに求められませんが、似たような感覚は今も生きていると思います。
アメリカ人の友人たちは「物凄い文化!!察しスキルとか空気読むとか、メンドクサッ!それができない人は一体どうやって生きていたの!」と驚きますが、日本は狭い島国。農耕民族が肩を寄せ合って生きていくのに、皆がハッキリものを言い合っていてはとても共存していけなかったのかもしれません。
対する英語の“love”は他動詞。loveの次にはyouとかhimとか、相手がいないとだめ。
誰が!誰を!どう思っているのか!すべてが明確に表現されます。
今では世界共通語としての地位を確立した英語ですが、500年ほど前まではイギリスとアイルランドでしか話されていないマイナー言語だったんです。大英帝国の拡大と共に世界各地に拡がり、独立したアメリカが大国になったことで世界共通語となりました。
特にアメリカでは、ヨーロッパ各地からの移民たちがお互い誤解のないよう思いを伝える手段として英語は最適だったのではないでしょうか。
英語の心は、「思ったことはどんどん言う。好きなら好きだと伝える。きちんと言葉にすることに意味があるから。」
日本語の心は、「あなたを思うと胸が温かくなる。焦がれて痛くなる。はっきりと言葉にはできない、しないけれど、あなたの隣で見る月はいつもより美しく見える。」
そんなまるで正反対の言語から生まれた、まったく同じような表現。
“Love is blind.” 恋は盲目。
“Seeing is believing.” 百聞は一見にしかず。
“All’s well that ends well.” 終わりよければ全て良し。
見た目や言葉や生い立ちがどんなに違っても、その真ん中でわかりあえるような気がしませんか?
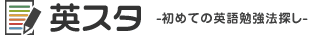






![[比較レビュー]スーパーエルマーvsヒアリングマラソン 英会話教材のNo.1決定戦。評価/評判。](https://i0.wp.com/www.ei-sta.com/wp-content/uploads/2017/10/elmavsmarathon.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)





















![[比較レビュー]スーパーエルマーvsヒアリングマラソン 英会話教材のNo.1決定戦。評価/評判。](https://i0.wp.com/www.ei-sta.com/wp-content/uploads/2017/10/elmavsmarathon.jpg?resize=100%2C70&ssl=1)




